歌人 北久保まりこ
鑑賞文・その他
鑑賞文・その他
これまで発表してきた、短歌・鑑賞文などを発表します。
[ AFTER FUKUSHIMA ]
1
when
will my later years
start?---
a mother cat has babies
at the ruined village
晩年はいつからならむ 廃村に親猫が子を産んでゐるなり
2
dim light
of cherry blossoms--
unstoppable
petal storm in the ruins
beyond my five senses
廃村に吹雪けるままの花明かりわれの五感を超えたるところ
3
sounds
of the stream
in my homeland---
Strontium is soaking
into the placenta
古里のせせらぎの音を思ひゐつストロンチウム沁むる胎盤
4
cherry avenue
my late mother's favorite...
is there
another world?
petal drift
吹き溜まるあの辺りから隠り世か亡母の好みし桜の並木
5
there were
days when I had
my dream...
are you there now?
Betelgeuse
われに夢ありし日在りき 今はもう亡いかもしれぬベテルギウスよ
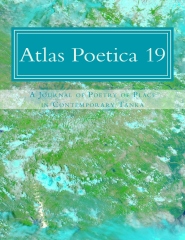
この度は Atlas Poetica 誌 Number 19 に連作を取り上げて頂き大変光栄に存じます。
今回は「アジアに関する題材」とのことでしたので過去に旅したベトナムに関する歌の連作をお出しいたしました。
【Atlas Poetica Number 19 に掲載された作者の皆様】
Contributors: Alex von Vaupel, Ana Prundaru, Anupam Sharma, Aruna Rao, Asni Amin, Autumn Noelle Hall, Barbara A. Taylor, Brian Zimmer, Bruce England, Charles D. Tarlton, Chen-ou Liu, David Rice, Debbie Strange, Ernesto P. Santiago, Genie Nakano, Gerry Jacobson, Grunge, Hannah Paul, Hema Ravi, Jade Pandora, Janet Qually, Joann Grisetti, Joanna Ashwell, John Tehan, Julie B. Cain, Kala Ramesh, Kath Abela Wilson, M. Kei, Mariko Kitakubo, Marilyn Humbert, Michael G. Smith, Natsuko Wilson, Nicholas B. Hamlin, Nilufer Y. Mistry, Patricia Prime, Pavithra Satheeshkumar, Payal A. Agarwal, Peter Fiore, Pravat Kumar Padhy, Radhey Shiam, Ram Krishna Singh, Rebecca Drouilhet, Richard St. Clair, Rodney Williams, Samantha Sirimanne Hyde, Sanford Goldstein, Sonam Chhoki
掲載された私の連作をご紹介します。
*本書には英文のみの掲載です。
title; [about Vietnam]
1
silent
deep black
soil--
dead jungle
were gods here?
(Northern part of Vietnam by cyclo)
*黒々と土は黙せり枯れ果てし密林に神はゐたのだらうか
2
Milky Way
like a sleeping Buddha
on the Mekong--
history is settling
in the bottom of the river
(by the Mekong of Vietnam)
*流されず過去は沈みぬ天の川涅槃のやうに映せるメコン
3
Halong Bay
is the mother of fog
harboring
the old silver scales
of dragons
(during the cruise of Halong Bay in Vietnam)
*ハローンは霧を産む湾いにしへの銀のうろこをどこかに隠す
4
searching for the gods
ousted from deep forests--
karst mountain
suddenly out
of the misty sea
(at the edge of Halong Bay)
*海上にカルスト聳ゆ深林を追はれし神を訪ねきたれば
5
in the distance
a heap of
jack fruits
look like skulls--
dust on the horizon
(at the twilight, in the rural of the North Vietnam)
*遠目には頭骨めける山売りのジャックフルーツ 地平の埃
父の記憶は私が八歳の春までで途切れる。
誰が悪いわけでもなく、物語が唐突に終わってしまうこともあるのだ。
お父様が居なくなっても大丈夫?うん、大丈夫よ・・・それが父との最後の会話ー。翌日、父の姿は本当に家から消えていた。まさか という驚きと後悔の念が押し寄せ、胸のなかで高波になった。今も小三の私は、あの縁側に立ったままだと感じるのは、紫陽花の咲く 父の日の頃。
後に孫の顔を見せたくて、母と共に父を探した。十五年前に亡くなっていたと知ったのは、随分と経ってからだ。
時間は止まったまま巻き戻せもしない。「ごめんなさい。あの時の応え、本当は嘘」実際に会うことができたら、そんな風に素直に話せ るかしら、などと仕様のないことを思ってしまうのは、決まってこんな猛暑の命日あたりだ。
この頃、ひょろりと背の高い息子の仕草が、父のそれに似て見える。
天国の父は私を許してくれたのだろうか。
水溜まりから雲がでてゆくやうにしてあの朝父はゐなくなりたり
『第七回国際交流短歌大会に参加して』
晴れやかに富士山を望む湘南にて開催された本大会は、私にとって第五回第六回に続き三度目の参加となった。回を重ねる毎に内容は深まり、短歌国際化の核に迫るものとなっている、というのが私の率直な感想である。
今回特記すべきは、モデレイターに三枝昴之氏、パネリストにアーサー・ビナード氏、秋山佐和子氏、中川佐和子氏を迎えて行われたパネルディスカッションである。普段から英文短歌に携わり、英訳や和訳を手懸ける私たちが直面し続けている、翻訳の壁への飽くなき挑戦について、今目前で真剣に議論されているという事実に心底感動を覚えた。
非力ながら、私が海外で和英や和仏による短歌朗読を始めて、今年で八年目になる。短歌より遥かに歴史の新しい俳句が、海外の教科書に各国の母国語で掲載されるほどの普及をみせる今、短歌もそろそろ、全世界に広く知られ愛されることを意識し始めても良い頃なのではないだろうか。
沖縄戦についてまだ詳しくは知らなかった私を受け入れ、平和を望む環の一員に加えて下さった沖縄の皆様に感謝し、稚拙ではあるがこの小文をお捧げしたいと思う。
[渡嘉敷島 -祈りの心で-]
「絶滅が危ぶまれる花なんですよ。」もう少しで見逃してしまいそうだった俯きがちな白い花を、ガイドさんが指差して教えてくれた―琉球千鳥蘭。よく観ると蘭特有の気品があり、小さいながらも凛として風情がある。渡嘉敷島にはその他にも、薔薇の原種を思わせる可憐な琉球薔薇苺の花や釣鐘草に似たサイヨウシャジンなど、自然のままの緑の中に、楚々と咲く花々がそこかしこにあり、初めて訪れた私を出迎えてくれた。
二月、この辺りはいつもなら雨の日が多いのだそうだが、麗らかな青空が広がっていた。
しかしそれとは裏腹に、私が受けとめなければならなかったのは、あまりにも陰惨な史実だった。
集団自決…それは恐らく、敵に八つ裂きにされるよりも辛い、あまりにも酷い現実であったろう。否、軽々しく“辛い”だの“酷い”だのという言葉で片付けてはいけない。
恐らく彼らは、死して尚忘れられぬであろう。自らの子に、時には乳児にまで手をかけざるを得なかった親たちの地獄を。また、老いた父母の、祖父母の弱々しい首筋に、縄を又は縒った草をかけた時の恐怖に震える己の手を。
彼らは、それまでの努力も成功も挫折も、そして手にしていた慎ましやかな幸いさえも、無残に抉り盗られた。この世に生を受けて以来の記憶のなかの、光の明滅のすべてを、そしてそれらを包み込む人生そのものを否定させられたのである。
飛び散る肉片が、血の海がそうさせたのか、私はその地に立った時、突然の腹痛に襲われた。しかし、歩を進められぬほどではなかったので、ゆっくりと友たちの後に続いた。
間もなく「アリラン慰霊のモニュメント」に到着すると、遠くに小鳥の声が聞こえ、程よい日差しが心地よかったが、それゆえにかえって歴史の物語る悲惨さが胸に迫った。
ガイドさんが、空色のモザイクで彩られた小ぶりのテラスをさし、「ここでは踊りや歌が披露されることもあるんですよ。」と言うと、皆が私にも朗読するようにと促した。突然の提案で、何の用意も無かったが、祈りの心を精一杯にこめて自作の短歌を朗読した。すると、普段パフォーマンス中には流したことの無い涙が溢れ、先ほどからの痛みも次第に消え去った。悲しめる魂たちを、少しでも慰めることができたのならば良いが…。ここは、唯々ひたに≪祈りの心≫でのみ訪れることの許される地であると、肌で感じた。
今からかれこれ十五年も前のことになるが、私が初めて息子を連れて沖縄を訪れた際、一番に見せたのは、瑠璃色の海でもなく、野生のヤマネコの愛らしい写真でもなかった。
空港から直に向かったのは、ひめゆりの資料館、そして摩文仁の丘だった。今でもそれは間違ってはいなかったと思う。沖縄は、そしてこの渡嘉敷は、何人たりとも祈りの心を忘れて、訪れては欲しくないところなのである。
本島へ戻るフェリーの座席で、今日一日を思い返し、デジカメ画像をチェックしていると、船内にアナウンスが響いた。「進行方向右前方に鯨を確認いたしました。」聞き終わらないうちに、私たちはデッキの手摺にしがみ付いていた。必死で懲らす肉眼に、悠然とした大きな鰭が見え、海原に雪のように白い飛沫が上がった。ああ、自然は、そして生きものは何と美しいのだろう。人間がこんなに醜い戦に明け暮れている間にも、花は咲き、動物たちは命を繋いでゆく。文明を築いたヒトが忘れ去り、思い出せぬ大切なことは、創造主に創られたままに、必要なだけを食べ、質朴に生きることではなかったろうか。
・絶望が火を加速する 殉死するために生まるる命など無い
・ラグーンに浮かぶ安らぎ 文明のつけた名前を知らないクラゲ
[伊江島「ヌチドゥタカラの家」を訪ねて]
山鳩の声ものどかな、緑深い伊江島の里に≪ヌチドゥタカラの家≫
資料館はある。雨上がりの土の香が、初めて訪れた私の心を和ませ、何か懐かしい気持ちにさせてくれた。
しかし、資料館の扉を開け、室内に一歩踏み込んだ時のあの衝撃を、脳裏から拭い去ることはできない。そこには、都会的な博物館などには無い、胸ぐらに掴みかかってくるような迫力があった。天井から吊るされた裂け目の目立つパラシュート、血だらけの乳児の肌着、大量の軍服、軍靴、弾丸、至る所からたってくる匂い。ガラスケースに納まること無く、まさにそこに在るモノたちから発せられる累累としたおびただしい念…。それらに、完全に押し潰されそうになりつつ、それでも部屋の奥へと進んだ。
「ここは、独りで来てはいけない場所だった。」という思いに襲われながら。でも、なぜか同時に、「否、独りではない。今私はあの戦争を知っている亡祖父母、亡父母、四人の亡伯父等と共に此処に立っている。」という、確信に近い不思議な感覚もあった。
今回の伊江島訪問は、歌人の先輩であり信頼する友でもある玉城洋子氏の提案により実現した。これまでに、アブチラガマ、ギーザバンタ、佐喜真美術館、渡嘉敷島、県立図書館、宮森小学校に足を運び、今後もさらに認識を深めようとする私に、「次には是非、伊江島へ。」とのアドバイスだったのだ。折しも「この島は沖縄戦の全てが語られている」と書かれた文献を、県立図書館で閲覧したばかりでもあった。そんな訳で、滞在中にぽっかりと予定の空いた一日を無駄にする手は無いと、早速朝から高速バスとフェリーを乗り継いで出掛けたのだった。
九年前に他界された阿波根昌鴻氏の養女・謝花悦子氏は、病院通いのお身体でありながら、私に二時間以上もの時を費やし、非暴力を訴え続けたここの創設者、阿波根氏について話して下さった。その穏やかではあるが芯の通った語り口にお養父様から受け継がれた生き様を垣間見た思いだった。
さらに私を感動させたことは、氏が生涯の目標として掲げておられた聖書の箇所が、私が最も好きな箇所として諳んじていた所と重なっていたことだ。キリスト教信者でなくても解り易い内容なので、ここで引用したいと思う。
※愛は寛容であり、愛は情け深い、またねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そして、全てを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える <-後略->
(コリント前書十三章より)
ご承知の様に男女の愛ではなく己を犠牲にする愛をさし、人のあるべき姿を説いている。
広い宇宙の中で、生命誕生のための希少な条件を満たしたこの星を「愛に満ちた星」とすることが、私たちにとって困難な、もしくは不可能なことであるのなら、それほど悲しむべきことはない。出会った者同士が殺し合うのではなく、出会えた奇跡に感謝し、お互いの素晴らしさを分かち合えたなら、と考えるのは、私やJ.レノンだけでは無いだろう。
・行かないで人を殺めに行かないで背中の羽も抜けきらぬ子等
・ほほ笑みを交せる奇跡 地球上たつた百年ほどの一生(ひとよ)に
・この星にともに生れし偶然よ木木も獣も魚もヒトも
握り飯を食いつつ見ている一滴の水に写れる世界のかぎり
掲出歌は「水」と題された二十四首の冒頭の作である。一連には、過去十年間に作者を残して逝った友人知人ら(岸上大作、伊藤栄治、高橋和巳、小野茂樹、三島由紀夫)の死にふれ、彼らの無念や、自らが生きること、歌うことに対する思いを綴った次のような文章が添えられている。
「(前略)生者にとっては絶対である死の世界からの彼らの働きかけに、言いわけし、許しを乞うみっともなさに自ら耐えることも、生きること歌うことを選ぶ者に必然な、生き恥、歌い恥なのだ。」
死者を意識した作品に、大きく心揺さ振られた。まず、極小レンズのような「一滴の水」に焦点をあわせてみる。すると、私たち生物が生命を維持するために不可欠であり基本的な、食するという行為が見えてくる。またそこには、作者が気にも留めていないような些細な諸事の一切と、時間のながれさえもが存在していた。あたかも、本人が気付く以前から設置されていた、盗撮カメラのように。
このことは、何気ない日常に隣り合わせている、死者たちの視線をも連想させる。もしかすると彼らは、それを通してこちら側を観、なにがしかの「働きかけ」を、無言のうちに試みているのかも知れない。
「絶対である死の世界」からすれば、生にしがみつく私たちは、さぞ滑稽で情けない姿として映ることだろう。この歌は、作者がそれを認め、背負って生きていく覚悟を固めた第一歩に他ならない。
ここで、関連のある作品を一首引いておきたい。
わが歌をすなわち生きる恥として若葉の中に溺れたきかな
(歌集『夏の鏡』より)
なんと骨太で、心地の良い歌なのだろう。この歌からは、掲出歌の根底に流れていた概念が、さらに深められた後の、作者の「生き恥、歌い恥」に対する、心理的な脱皮が感じられる。それを諦念としてではなく、肯定的にとらえて引き受け、達観した心境で堂々とうたうことにより、読者にこのうえない爽快感を与えられるのだと思うからである。
ここ十数年間で、身近な親族のほぼ全員が他界した私にとって、<死>は遠い出来事ではなくなっていた。ふとした瞬間に、たとえば庭に大水青がやって来るように、いとも自然に音もなく、それは舞い降りるものだ。帰りつくよりどころを失い、独り「恥」を抱えて日々を送ることに慣れてしまっていた私には、こうした作品に出会えることが、共有する安堵感を得、またポジティブな思考へいざなわれるという意味で、大きな救いでもあり、幸いなのである。
「あとがき」に「白い糸で綴じたものが死後にそっとみつかる、というのが憧れ」だったとある。
米国・バーモントの自然の中で詠まれた作品が、一ページに一首ずつ、英訳と見開きで、贅沢に収められている。
作者の生きた温もりを感じさせる作品が目をひいた。
・温泉はなけれど我の湯船には肌柔らかな歌う子のいて
・あかさたなと兄が言えば妹があかさかな「赤魚」と歌う
・「みのむし」と寝言をいったといわれけり宙ぶらりんの自分をみたか
・近道のはずが田舎の道にでて山美しく遠回りする
・かすかなる風のあしあと落ち葉道
・冬の雨おかめいんこのひとりごと
また、心の中にみちてきた思いを、二つの言語で表すことで、この一冊を受け入れる読者の幅が、どれだけ広がるかを作者は知っている。
そして恐らく、それによるリスクを引き受けることも、覚悟しているのだろう。
私は、和英対訳歌集を編む一人として、彼女の静かな、しかし勇気ある一歩にエールを送りたい。
今後は、この穏やかに呼吸するような詠いぶりに、揺るぎない個性が加わり、さらに完成されていくことを、心から祈っている。
これは、二千六年パリで出版された皇后陛下美智子様の御歌の仏語訳、御歌撰集『セオトーせせらぎの歌』(五十三首)に、世界から寄せられた反響を綴ったレポートである。
その一部を紹介すると、フランスのシラク前大統領より、〈和歌のもつ息吹の力と、魂の昂揚力とが絶妙に表現されている〉と賞賛の便りが届いた。また、同国の隔月誌『新歴史評論』主幹のD.ヴェーネル氏は、同誌・特集「日本のサムライ」の中で、〈これらの調べこそ、つつましき情感をもって歌われた永遠の大和魂への讃歌である〉と語っている。
絶賛の声は、はるかアフリカ大陸からも聞かれた。ルワンダで、青少年育成に力を注ぐO.デュクロ氏は、〈アフリカもまた、霊に重きを置く文明なのだ〉としたうえで、〈コトダマと呼ばれる崇高な精神を宿している御歌を、アフリカ中に伝え、青少年の情操に役立てるべきだ〉と講演した。すると、それに感動した、ルワンダ大学前教授は、御歌のポルトガル語訳にも乗り出したという。
興味深いのは、自ら仏語訳を手掛けた著者が、〈詩の翻訳とは、詩人と形影相伴う仲での影である〉と述べている点である。そして、一読者である私も、原作・日本語の放つ神秘性を再認識し、深い敬意を感じずにはいられなかった。
斯くして、日本から発せられた慈愛と祈りの言霊は、言語、国境を越えて世界と響き合い、今もなおその波紋は広がり続けている。
五月のバンクーバーの空は、透明な水色をしていた。日本から一人で訪れた私を迎えてくれたのは、針葉樹の匂いと野生の栗鼠だった。
雪を頂いたカナディアンロッキーを遥かに望むUBC(ブリティッシュコロンビア大学)が、今回の会場である。案内された宿泊棟はこざっぱりとした寮で、五泊六日の滞在は、遥々赴いた留学生の気分で始まった。
初日に開かれたパーティで、五・六十名の参加者が顔を合わせた。殆どがカナダ、アメリカ在住の短歌や俳句の愛好家である。互いに著書の紹介などを交わすうちに、和やかに打ち解け心地よい滑り出しとなった。
時差も手伝い、目蓋が重くなってきた夜十時、連句の会は始まった。私は出発前から、日程表のRenkuの文字がとても気になっていた。まず、本来なら五七五の次は七七と続けてゆくものを、英文でどうやるのか?要となる<捌き>を努める人間は居るのか?大体、英文で連句が楽しめるものだろうか?
しかし蓋を開けて、彼らの認識の深さに感服してしまった。まず、捌きがきちんと発句を提示し、次の句の指示を出したのである。発句が<三行>で次は<二行・春の花の句>という指示だった。集まった十五・六名は、挙ってそれに挑んだ。私は、彼らに失礼な考えをもっていたことを恥じながら、一生懸命に作った。一首でも捌きの目に留まる句が作りたい・・・連句の楽しみは言語の違いを超えていた。どこからともなく月桂冠の一升壜が出てくるあたりも、日本人が旅先でする連句宛らであった。
月の句、恋の句と皆で夢中になって作り進むうち、時計の針は深夜一時を回った。それでも一向に終わる気配も無く、誰も席を立たない。ここで日本人が寝てしまうわけにはゆかぬと私も頑張った。結局、二時半を回ったところで三十六首を完結し、全員から拍手がわき起こった。
駆け足の連句ではあったが、彼らの熱意に対し、ありがとうといいたい気持ちになって床に就いた。
私の今回の旅の目的である短歌朗読は、最終日の日程に組まれていた。翻訳から意味をくみとるだけでは得られない何かを、ぜひ彼らに感じとって欲しかった。
具体的な方法としては、まず日本語で一首読み、五七の音を感じて貰う。次に英語で読み、内容を理解して貰う。そのうえで、もう一度日本語で読み、韻律を味わって貰う、という三部構成で行った。
内容は対訳歌集『On This Same Star』より人間の愛・生・死という普遍的なテーマの作品と、二十年前のチェルノブイリの事故に因んだ作品の、合わせて二十五首である。
実際に読み始めると、聞き手の感動がジンジンと伝わってきた。国内で、これまでに何度も朗読をしてきたが、これほどの手応えと一体感は初めてだった。その情熱に突き動かされ、心の深みから朗読してゆくと、たくさんの魂が会場内で大きな渦になったような気がした。
そして「また聴きたいから来年も来て欲しい」と言われたことと、何人もから、熱っぽく”emotionalだった”という感想が得られたことが、この上なく嬉しかった。実際、廊下ですれ違う面々に、次々にハグされるほどの反響は、私自身想像もしていなかったことである。
これからも望まれれば、可能な限り出掛けていって、こうしたパフォーマンスを続けていきたいと思う。そして何より、国籍、性別、年齢を問わず、心と心に響き合う歌を作り続けたいと願っている。
歌集『谷汲』より
生きてあらば二十七歳その母に言はんとぞして口を噤みぬ
(夏・哀傷 澄高禅童子二十年忌より)
長男・高志の二十年忌に詠まれた歌である。幼いわが子に先立たれた心情は、察するに余りある。時を経ても 癒されぬ喪失感が、作品から滲んで止まない。
親族や近しい人たちを、相次いで亡くした修にとって、高志の誕生は、闇に差す光そのものであっただろう。しかしその新しい命までも、たった数年で奪われるという悲運に、見舞われてしまったのである。
毎年命日が巡る度に、修と「その母」は、あの夏の日へと引き戻される。二人は、現実の日々を生きながら、もう一つの、二十年前に止まってしまった時間を、抱えているのである。そして、「生きてあらば」と、その歳の頃を思い、青年になっているはずの子の姿を、霞のようにみるのであった。死者と生者の間に横たわる、混沌とした時を通して、無限の奥行を感じさせる作品である。
修は、「その母」に言いかけたうわ言のようなことばに「口を噤み」、止まった時の振り子の前に蹲っている。そしていつしか、一読者である私も、その動かぬ時を共有していることに、気付かされたのであった。
 前のページへ
前のページへ- 次のページへ

